「生前墓って何?」「メリットはあるの?」「なんだか縁起が悪そうだけど大丈夫?」
こんな悩みを抱えてはいませんか?
終活などの際に話題になる生前墓ですが、いざ建てようとすると縁起が悪いのではないかなど不安や疑問も出てくるものです。
この記事では、生前墓を建てるメリットやデメリットについて詳しく解説しています。
縁起が悪いという噂や注意点も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
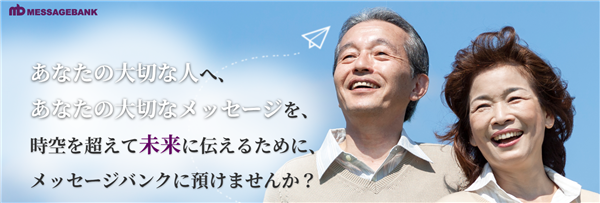
終活を進めるなかで生前墓をはじめとして、家族に共有しておきたいことも出てくるでしょう。
終活の意向についてまとめておくための方法としてエンディングノートが用いられるケースが多いですが、エンディングノートは確実に家族の手に渡らない可能性がある点がデメリットです。
弊社が展開するサービス『メッセージバンク』は家族や友人へのメッセージをあらかじめ預けておき、好きなタイミングで送信できるサービスです。
あらゆる項目ごとにメッセージを作成することができるので、エンディングノートとして利用してお墓や葬式、相続に関してまとめておけばそのまま任意のタイミングで家族に送信できます。
確実に家族がメッセージを確認してくれるので、もしあなたに不幸が訪れてもエンディングノートを見つけてもらえるか不安になる必要はありません。
預けておけるデータは様々なファイル形式に対応しているので、動画や音声ファイルで家族に感謝のメッセージを遺すこともできますよ。
終活の手助けとなるメッセージバンクが気になる人は、下記より詳しい説明を見てみてくださいね。
生前墓とは?縁起が悪いの噂

まずは生前墓について解説します。
結論、生前墓は縁起が悪いものではありません。
生前墓とは生きているうちにお墓を建てること
生前墓とは生きているうちに自分のお墓を建てることで、読み方は「せいぜんぼ」と読みます。
現在は終活を行う人も多く、近年では家族に迷惑をかけたくないと生きているうちに自分のお墓を用意する人も少なくありません。
実際に様々な霊園では生前墓の予約や申込みが増加している事実もあるほどです。
生前墓は縁起が良い行為
生前墓は自分が生きているうちに自分のお墓を作るので、「縁起が悪い」と思う人もいますが、実は縁起の良い行為でもあるのです。
生前墓は中国では「寿陵」とも呼ばれ、建てることで長寿を招くと信じられています。
また長寿以外にも「家庭円満」や「子孫繁栄」といったご利益もあるとも伝えられているので、かの有名な秦の始皇帝も自分の生前墓を建てたと言われています。
仏教でも自分の冥福を祈る徳の高い行為と言われているので、過度に心配する必要はないでしょう。
聖徳太子も徳を高めるために生前墓を建てたと言われているので、むしろ縁起の良い行為です。
生前墓を建てるメリット

生前墓は縁起が良い以外にも、多くのメリットがあります。
メリットを理解して生前墓を建てるか判断しましょう。
終活になるので家族に迷惑がかからない
生前墓は亡くなる前に自分のお墓を建てられるので、遺される家族に迷惑がかかりません。
費用も自分で支払うことになるので、時間や手続き以外にも経済的な面で家族に負担を強いることを防げます。
あなたが亡くなったとき、家族は精神的にも苦しい状況になるでしょう。
悲しい思いをしながらお墓の準備なども進めなければいけないのは、相当な負担になるものです。
あらかじめお墓を準備しておけば、スムーズに手続きを進められ、家族が喪に服する時間を確保してあげることもでき、気持ちを切り替えやすいでしょう。
自分が思ったお墓や埋葬方法を選べる
生前墓を建てておくと、自分でお墓のデザインや埋葬方法を選ぶことが可能です。
近年では、お墓のデザインも多種多様となってきており、自分が素敵だなと思えるお墓を建てることができます。
また埋葬方法もいわゆる一般的な納骨以外に、樹木葬や散骨など様々な方法があります。
自分が思ったとおりの埋葬方法を選べるので、より納得した形で最期を迎えられるでしょう。
節税対策になる
墓地や墓石、仏壇などは財産に分類されますが、相続税はかかりません。
あらかじめ自分のお墓のための費用を渡しておくことも可能ですが、現金のやりとりの場合は相続税や贈与税などの税金がかかってしまいます。
生前墓でお墓を建てて子どもなどに相続することで、無駄な相続税を抑えることが可能です。
必要なお金の計算ができる
生前墓を検討することで、今後必要となるお金の計算がしやすくなります。
お墓や葬儀は大きなお金がかかるものなので、それらの費用が明確になれば老後にかかる費用をどれくらい準備しておけばよいのかなど計算できるでしょう。
特に40代や50代などの若いうちから検討を始めれば、老後費用も明確になり積み立てを始めるなど対策も立てられます。
つみたてNISAやiDeCoを始めるなどすれば、十分費用を貯められるでしょう。
生前墓を建てるデメリット・注意点
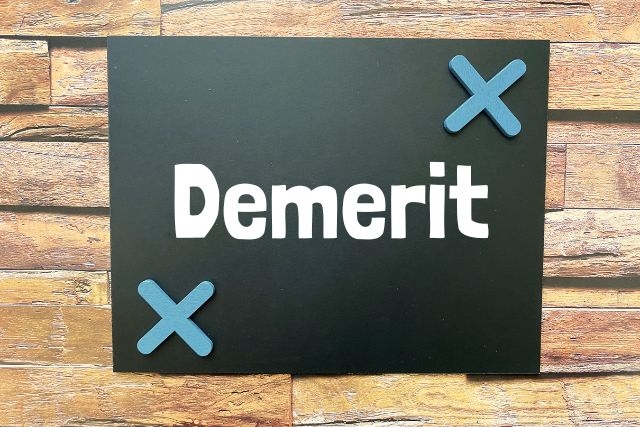
生前墓を建てるメリットは多いですが、デメリットがあるのも事実です。
ここでは生前墓を建てるデメリットを紹介します。
生前墓を受け付けているお墓が限られる
生前墓は受け付けている霊園などに限りがあるので、必ず自分が望む場所にお墓を建てられるわけではありません。
公営墓地など管理費等が安く利用者が多い墓地は、遺骨がないと利用できないケースもあります。
事前に生前墓の建立が可能か確認してから、話を進めるようにしましょう。
ローンや管理費などは計画的に考えておく
お墓を建てるためには、まとまったお金が必要になりますが、ローンや管理費については計画的に考えておくことが必要です。
万が一ローン支払い中にあなたが亡くなった場合は、家族が代わりにローンの返済を行っていくことになり、結果として迷惑がかかってしまうケースもあり得ます。
ローンを組む際は、亡くなる前に完済できるよう無理のない返済計画を建てましょう。
また意外と忘れがちなのが、生前墓の管理費です。
相場は利用するお墓によって大きく変わりますが、年間2,000円~15,000円程度かかるので注意が必要です。
相談なしに決めるとトラブルに発展することも
生前墓を建てる際は、家族や親族に事前に相談しないとトラブルに発展することもあります。
特にすでにお墓があるにも関わらず、別で自分だけの生前墓を購入する際は注意が必要です。
家族の意向では「みんなで同じお墓に入りたい」と考えている場合もあるので、事前に必ず相談しましょう。
またお墓がない場合でも、お墓参りがしやすい場所などを家族と一緒に決めた方が後々のトラブルを回避できます。
生前墓の費用相場はいくら?

生前墓は亡くなる前だからといって費用が安くなるなどはなく、お墓の種類によって必要な費用がかかります。
具体的には、下表を参考にしてください。
| お墓や葬儀の種類 | 説明 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 継承墓 | 先祖代々受け継がれていくお墓。 お墓を建てる霊園や地域によって金額が大きく変わる。 | お墓費用:150万円~200万円程度 管理費:5,000円~1万5,000円程度 |
| 永代供養墓(個別供養なし) | 個別のお墓はなく、大きな供養塔に祀られる。 費用が抑えられ、管理費もかからない。 | お墓費用:30万円程度 管理費:無料 |
| 永代供養墓(個別供養あり) | 一定の契約期間内は個別で供養できるようにしておき、契約が切れたタイミングで供養塔に移動される。 個別供養なしと比べると費用は高く、管理費がかかるケースもある。 | お墓費用:100万円~200万円管理費用:5,000円~1万5,000円 |
| 樹木葬 | 墓石ではなく樹木の元に埋葬する方法。 区画内に希望の樹木を植えられることもあり、費用相場も幅広い。 管理費は亡くなる前に発生するケースが多い。 | お墓費用:30万円~150万円管理費用:1万円 |
| 納骨堂 | 施設内に骨壺を収容しているタイプのお墓。 コインロッカータイプのものもあれば、IDなどを元に自動的に骨壺が運ばれてくるタイプなど様々。 1か所に家族の遺骨をまとめられるタイプなどは高くなる傾向。 | お墓費用:30万円~100万円 管理費用:1万円~2万円 |
相場費用は立地や納骨方法で大きく変わるので、自分の予算に合わせて選びましょう。
生前墓を建てる具体的な方法

生前墓を建てるには、以下の手順で手続きを進めていきます。
墓地に問いあわせる
生前墓を建てる墓地に問い合わせします。
墓地によっては生前墓に対応していないケースもあるので、事前に確認しておきましょう。
公式HPから資料請求したり、電話で問い合わせたりして確認を取ると確実です。
その際は宗教や宗派などの指定の有無もチェックしておくと良いでしょう。
霊園見学を行う
資料や問い合わせで候補を絞った後は、霊園見学を行いましょう。
霊園の日当たりや景色など園内の様子を確認して、自分が納得できる場所を選びます。
事前に確認しておきたいことがある場合は、見学中に質問しておくのがおすすめです。
申し込み手続きをする
霊園見学で納得できる場所が見つかったら、申込み手続きを行います。
区画利用の権利や使用料の支払いなどを行うので、このタイミングでお金を準備しておきます。
また本人確認書類の提出が必要なので、住民票などを準備しておくのも忘れてはいけません。
手続きが完了した後は「永代使用承認証」が発行されるので、生前墓の建立が可能です。
石材屋で墓石を建てる
区画が決まったら、石材や墓石を建ててもらいましょう。
多くの場合は霊園付近に石材屋があるので、デザインや刻印する文字などを決めて見積もりを出します。
契約内容に納得ができたら実際に墓石を作成して、3ヶ月程度で建立が完了します。
生前墓の建碑式にいくら包む?
生前墓は建設が終わった場合は、お坊さんを呼んで建碑式という法要を行うケースがあります。
別名、開眼法要とも呼ばれお祝いの式典としての扱いになるので、呼ばれた倍は建碑祝いを渡すのが通例です。
金額の相場は家族なら2~3万円、友人の場合は1万円程度と考えておくと良いでしょう。
ただし納骨と同時に行なわれる場合は、仏事の扱いとなるため「ご仏前」を渡します。
生前墓に関するよくある質問

最後に、生前墓に関するよくある質問を紹介します。
生前墓に関する疑問をすべて解消して、手続きを進めましょう。
- Qお墓を建ててはいけない年ってあるの?
- A
基本的にお墓を建ててはいけない年はありません。
過去にはうるう年は大きな買い物をしてはいけないと言われた時代もありますが、現在はそこまで気にする必要はないでしょう。
ただし六曜を気にする場合は、赤口や仏滅は避けた方が良いでしょう。
- Q2023年のお墓を建てるのに良い日は?
- A
縁起を気にするのであれば、暦注の十二直の閉の日が良いとされています。
2023年の場合は、以下の日付が十二直の「閉」にあたるので、お墓を建てるのに向いているでしょう。
- 1月5日(木)
- 1月6日(金)
- 1月18日(水)
- 1月30日(月)
- 2月12日(日)
- 2月24日(金)
- 3月9日(木)
- 3月21日(火)
- 4月2日(日)
- 4月15日(土)
- 4月27日(木)
- 5月10日(水)
- 5月22日(月)
- 6月3日(土)
- 6月16日(金)
- 6月28日(水)
- 7月11日(火)
- 7月23日(日)
- 8月4日(金)
- 8月17日(木)
- 8月29日(火)
- 9月11日(月)
- 9月23日(土)
- 10月5日(木)
- 10月18日(水)
- 10月30日(月)
- 11月12日(日)
- 11月24日(金)
- 12月6日(水)
- 12月7日(木)
- 12月19日(火)
- 12月31日(日)
ただし上記の中でも、赤口と仏滅は縁起が悪いとされるので避けた方が無難です。
- Q生前墓を建てた後は適度にお参りした方がいいの?
- A
生前墓であっても適度にお参りするのがおすすめです。
生前であっても開眼供養した場合は、すでに仏となっているという考え方なのでお参りするのが良いでしょう。
生前墓のお墓参りは徳が高い行動とも言われているので、お墓の掃除などをするついでにお参りもしておくと気持ち的にもさっぱりします。
生前墓は縁起が良い!終活の一環として始めよう
生前墓は縁起の良いことなので、気にする必要はありません。
むしろ家族に迷惑がかからないなどメリットも多いです。
「自分が死ぬ前に家族に迷惑をかけたくないな」と思っている人は、ぜひ終活をはじめてみましょう。
終活についてより詳しく知りたい人は、下記記事も参考にしてくださいね。



